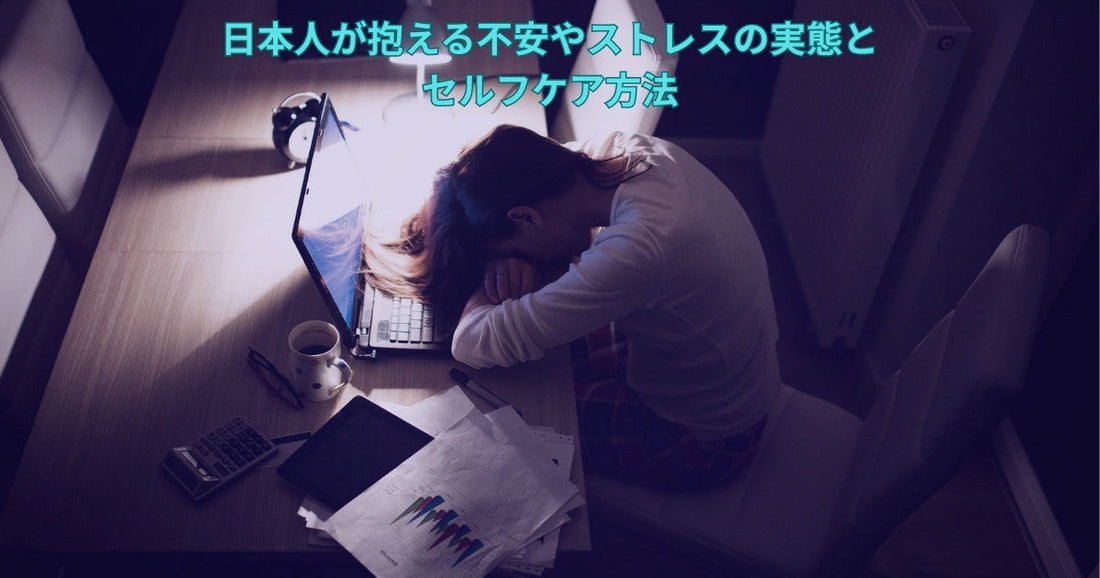
日本人が抱える不安やストレスの実態とセルフケア方法
SNSで共有
「いつも疲れている」日本人
「なんとなくずっと疲れている」「眠りが浅い」「仕事や将来のことを考えると胸がざわつく」
そんな感覚は多くの日本人の「日常」になりつつあります。
実際、日本の労働者では「仕事や職業生活に関してストレスを感じる」人が非常に多いことが厚生労働省の調査からわかっています。
たとえば、直近の労働安全衛生調査では、ストレスの相談先として「家族・友人」「同僚」「上司」などが挙げられ、実際に相談したことがある人も7割前後に達します。
職場の人間関係・仕事量・会社の将来性などが主要因で、いわば「構造的なストレス」を抱えやすい環境が背景にあります。
引用:厚生労働省+1
また、日常生活の不安感も高い水準です。
内閣府の「国民生活に関する世論調査」では、悩み・不安を抱える人が多数派である状況が続いており、家計・健康・老後など身近なテーマが不安の種として並びます。
コロナ禍や物価上昇を経て、先行きへの漠然とした不安が下支えしていると見られます。
では、私たちはこの「慢性化しやすい不安・ストレス」とどう付き合えばよいのでしょう。
ポイントは、「①体内リズムを整える」「②「いま」できる緊張ほぐし」「③話す・頼る」の三本柱です。
体内リズム
朝の光で体内時計を整え、夜は光を落として副交感神経にバトンを渡す――これは睡眠ガイドも推奨する基本です。
就寝前はスマホや強い照明を避け、寝室の明かりを暖色の間接照明に切り替えると、眠気(メラトニン)の流れを妨げにくくなります。
緊張ほぐし
数分の「マイクロブレイク(小休憩)」や軽いストレッチ、深呼吸でもストレスは目に見えて下がります。仕事の合間に立ち上がって肩回し・首伸ばし、呼吸は5秒吸って5~7秒吐くリズムを数回。短時間の運動をはさむ介入で、仕事ストレスが低下した研究報告もあります。
引用:ビジネスリサーチラボ
話す・頼る
悩みを言語化して共有するだけで、情動の整理と安心感の回復が起こります。
厚労省調査でも「家族・友人・同僚」に相談する行動が多く、相談経験は7割に達します。
社内の産業医や外部の相談窓口、地域のメンタルヘルス支援も遠慮なく活用しましょう。
セルフケアを生活に組み込むコツは、「ハードルを下げて「できること」から行う」ことです。
たとえば、夜は湯船に浸かり(就寝90分前が目安)、上がったら照明を落としてストレッチ、枕元にはラベンダーのピローミスト
これだけでも、交感神経優位から副交感神経優位へのスムーズな切り替えが促されます。
入浴のタイミングは睡眠研究でも支持される実践です。
引用:PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
安眠に導くツール
道具の力も借りましょう。
かち旅でも取り扱っている「おやすみハーモニー」のようなリラックスデバイスや、首を支える「ぐっすりネックサポート枕」、温冷で頭をいたわる「ぐっすり温冷リリーフキャップ」は、感覚刺激(音・圧・温度)を通じて緊張を下げ、入眠儀式の「合図」になります。
睡眠ガイドでも、生活習慣と環境(光・温度・静けさ・寝具)の調整を柱に据えています。
専門家によるサポート
もちろん、気分の落ち込み・不眠が長引く、仕事や生活に支障が出る
そんなときは専門家にご相談を。
慢性不眠の第一選択はCBT-I(不眠症の認知行動療法)で、国内公的情報でも強く推奨されています。
引用:厚生労働省eJIM「統合医療」情報発信サイト+1
【参考文献】
・厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」令和5年・令和4年の概況(PDF)厚生労働省+1
・内閣府「国民生活に関する世論調査(令和6年)」survey.gov-online.go.jp
・PRESIDENT Online「入浴後90分で就寝」西野精治氏インタビュー要旨(2019)PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
・厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」厚生労働省
・厚生労働省eJIM「睡眠障害に対する心身療法/CBT-I」厚生労働省eJIM「統合医療」情報発信サイト+1
・BRLab「マイクロブレイクの可能性」レビュー(2024)https://www.business-research-lab.com/240515/


